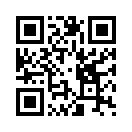続・館長ブログ「吉の浦だより」
「沖縄のオカヤドカリ展」開催にあたってのごあいさつ(吉の浦だより46)
夏になるとBBQや海水浴などで海辺に出かける機会が多くなります。そんな時出会う生き物の代表格がオカヤドカリ、すなわちアーマンではないでしょうか。このオカヤドカリ、沖縄ではそこら中の海岸にゴロゴロしていますが、実は国指定の天然記念物なのです。文化財としてはヤンバルクイナやジュゴンと同格ということになります。ありふれているが重要という二面性を持っている訳ですね。また、汚物をあさる不浄な動物と見なされることがあるかと思えば、地域によっては人間の祖先で神聖な存在であったりもします。人間からこれだけ矛盾するようなイメージを持たれている生き物はオカヤドカリをおいて他にはないと思います。

ナキオカヤドカリ
八重山の創世神話では、神がはじめにアーマンを作りました。アダン林の地面の穴から「カブリー」と叫んでアーマンが飛び出し、アダンの実を食べて繁殖していきます。神は次に人間の男女を作るのですが、この男女はアーマンと同じ穴から生まれます。そして、やはり「カブリー」と叫んで飛び出してくるのです。この場合、オカヤドカリは人類の始まりに生じる「不完全な子」であり、古事記におけるヒルコ、ミクロネシア神話におけるシャコガイに相当すると考えられます。かつて琉球に針突(ハジチ)の習慣があった頃、沖永良部島や多良間島の女性たちは左手首の尺骨茎状突起にオカヤドカリの模様を入れていました。彼女たちは「自分たちはアーマンの子孫なので入れている」と語り、オカヤドカリが人間の始まりであるという八重山の神話と相通ずる考えを示したのです。

オオナキオカヤドカリ
オカヤドカリは沖縄では非常に個体数が多く、採るのはいたって簡単です。ところが、昔から食べられた形跡が余りありません。沖縄戦中、あるいは戦争直後の食糧難の時代でさえほとんど食べられていません。この時期アフリカマイマイが積極的に利用されたのと対照的です。自分たちの先祖であるから食べなかったのか。あるいは、オカヤドカリが動物の糞などを食べるために忌避されたのか。かつて風葬のあった時代にはオカヤドカリが遺体に群がっている所を見た人もいたことでしょう。柳田国男は「オカヤドカリは姿形からして奇怪、妖魔の使者を思わせる。暗所を好み汚物に集まる習性がある。そのため、伝説すなわち最初に土中より出ずるという話が先島にうまれた」とメモに記しました。柳田の考えによれば、姿かたち、暗所・汚物を好む性質が、オカヤドカリを聖なる存在にしたことになります。

オカヤドカリ
一方、オカヤドカリは昔から子どもたちの遊び相手でもありました。日本本土では、戦前から主に露天商が街頭で売っています。明治期の文筆家大町桂月は、隅田川吾妻橋の袂でオカヤドカリ売りを見かけ「児等の為に買ふ」と随筆に書いています。オカヤドカリの販売に驚く様子は無く、目新しさを示す表現もありません。この文章が載った『閑日月』は明治41年刊行ですが、この頃までにはすでに繁華街でのオカヤドカリ売りは日常的な光景になっていたのでしょう。オカヤドカリは熱帯・亜熱帯の生き物なので、戦前期本土で販売されていたオカヤドカリの主な産地は小笠原、奄美・沖縄と思われますが、「ヤップ島から運んでいる」という新聞記事もあります。子どものペットとしての販売は戦後も盛んで、新宿、銀座などの繁華街では日常的に、その他社寺のお祭り、花火大会などの際に洗面器にオカヤドカリを入れた露天商を見かけたものです。そのピークは1960~1970年代という印象です。

ムラサキオカヤドカリ
1968年、小笠原が本土復帰しました。この頃、国、東京都、各大学がそれぞれ調査団を小笠原に派遣し、その結果、小笠原の価値の本質として貴重な自然と固有生物が強調されました。小笠原の本土復帰に際して最も懸念される事項は環境破壊と小笠原固有種等の乱獲だったのです。この状況において文化庁は1968、1970年に計16件の小笠原の動物を「地域を定めない天然記念物」に指定します。このうち15件は小笠原固有の動物あるいはそれを含む動物群であり、オカヤドカリだけが小笠原固有でない動物でした。オカヤドカリは東京などへの移出・販売用にすでに大量に捕獲されており、復帰後その状況がさらに悪化することが懸念されたため指定されたと思われます。

コムラサキオカヤドカリ
1980年代以降、街でオカヤドカリ売りをあまり見かけなくなります。ペットショップの充実と関係がありそうですが、正確なところは分かりません。その後、子どもたちの遊びがTVゲーム中心に移行し、オカヤドカリと子どもたちの関係は希薄になっていきます。2000年代になるとオカヤドカリはネットを介して世界中に流通するようになります。子どものおもちゃというより大人の趣味の対象として、というカタチです。現在、カリブ海諸島ではアメリカへの輸出用に大量に捕獲されているし、タイでは、法規制がない中で乱獲され減少が心配されているところがあります。昨年、沖縄でも密漁者が摘発されたのをご記憶の方も多いと思います。自然海岸の開発と相まって、沖縄のオカヤドカリに関してもそう楽観していられない状況になりつつあるようです。
ありふれた生き物ではありますが、人間の歴史文化に深いかかわりを持つオカヤドカリ。社会におけるこの生き物への理解と保護が進むことで、いつまでも「ありふれた天然記念物」を持続して行くことができればと思います。本企画展が、皆様のオカヤドカリに対する興味関心を持つきっかけとなれば幸いです。
本企画展を開催するにあたり、奄美市立奄美博物館、南方熊楠顕彰館(和歌山県田辺市)、沖縄県立博物館・美術館、琉球大学風樹館、沖縄オカヤドカリ取扱商組合、沖縄県教育庁文化財課から資料や情報の提供などご協力を賜りました。厚く御礼申し上げます。
(文責:濱口寿夫)
ナキオカヤドカリ
八重山の創世神話では、神がはじめにアーマンを作りました。アダン林の地面の穴から「カブリー」と叫んでアーマンが飛び出し、アダンの実を食べて繁殖していきます。神は次に人間の男女を作るのですが、この男女はアーマンと同じ穴から生まれます。そして、やはり「カブリー」と叫んで飛び出してくるのです。この場合、オカヤドカリは人類の始まりに生じる「不完全な子」であり、古事記におけるヒルコ、ミクロネシア神話におけるシャコガイに相当すると考えられます。かつて琉球に針突(ハジチ)の習慣があった頃、沖永良部島や多良間島の女性たちは左手首の尺骨茎状突起にオカヤドカリの模様を入れていました。彼女たちは「自分たちはアーマンの子孫なので入れている」と語り、オカヤドカリが人間の始まりであるという八重山の神話と相通ずる考えを示したのです。

オオナキオカヤドカリ
オカヤドカリは沖縄では非常に個体数が多く、採るのはいたって簡単です。ところが、昔から食べられた形跡が余りありません。沖縄戦中、あるいは戦争直後の食糧難の時代でさえほとんど食べられていません。この時期アフリカマイマイが積極的に利用されたのと対照的です。自分たちの先祖であるから食べなかったのか。あるいは、オカヤドカリが動物の糞などを食べるために忌避されたのか。かつて風葬のあった時代にはオカヤドカリが遺体に群がっている所を見た人もいたことでしょう。柳田国男は「オカヤドカリは姿形からして奇怪、妖魔の使者を思わせる。暗所を好み汚物に集まる習性がある。そのため、伝説すなわち最初に土中より出ずるという話が先島にうまれた」とメモに記しました。柳田の考えによれば、姿かたち、暗所・汚物を好む性質が、オカヤドカリを聖なる存在にしたことになります。
オカヤドカリ
一方、オカヤドカリは昔から子どもたちの遊び相手でもありました。日本本土では、戦前から主に露天商が街頭で売っています。明治期の文筆家大町桂月は、隅田川吾妻橋の袂でオカヤドカリ売りを見かけ「児等の為に買ふ」と随筆に書いています。オカヤドカリの販売に驚く様子は無く、目新しさを示す表現もありません。この文章が載った『閑日月』は明治41年刊行ですが、この頃までにはすでに繁華街でのオカヤドカリ売りは日常的な光景になっていたのでしょう。オカヤドカリは熱帯・亜熱帯の生き物なので、戦前期本土で販売されていたオカヤドカリの主な産地は小笠原、奄美・沖縄と思われますが、「ヤップ島から運んでいる」という新聞記事もあります。子どものペットとしての販売は戦後も盛んで、新宿、銀座などの繁華街では日常的に、その他社寺のお祭り、花火大会などの際に洗面器にオカヤドカリを入れた露天商を見かけたものです。そのピークは1960~1970年代という印象です。
ムラサキオカヤドカリ
1968年、小笠原が本土復帰しました。この頃、国、東京都、各大学がそれぞれ調査団を小笠原に派遣し、その結果、小笠原の価値の本質として貴重な自然と固有生物が強調されました。小笠原の本土復帰に際して最も懸念される事項は環境破壊と小笠原固有種等の乱獲だったのです。この状況において文化庁は1968、1970年に計16件の小笠原の動物を「地域を定めない天然記念物」に指定します。このうち15件は小笠原固有の動物あるいはそれを含む動物群であり、オカヤドカリだけが小笠原固有でない動物でした。オカヤドカリは東京などへの移出・販売用にすでに大量に捕獲されており、復帰後その状況がさらに悪化することが懸念されたため指定されたと思われます。

コムラサキオカヤドカリ
1980年代以降、街でオカヤドカリ売りをあまり見かけなくなります。ペットショップの充実と関係がありそうですが、正確なところは分かりません。その後、子どもたちの遊びがTVゲーム中心に移行し、オカヤドカリと子どもたちの関係は希薄になっていきます。2000年代になるとオカヤドカリはネットを介して世界中に流通するようになります。子どものおもちゃというより大人の趣味の対象として、というカタチです。現在、カリブ海諸島ではアメリカへの輸出用に大量に捕獲されているし、タイでは、法規制がない中で乱獲され減少が心配されているところがあります。昨年、沖縄でも密漁者が摘発されたのをご記憶の方も多いと思います。自然海岸の開発と相まって、沖縄のオカヤドカリに関してもそう楽観していられない状況になりつつあるようです。
ありふれた生き物ではありますが、人間の歴史文化に深いかかわりを持つオカヤドカリ。社会におけるこの生き物への理解と保護が進むことで、いつまでも「ありふれた天然記念物」を持続して行くことができればと思います。本企画展が、皆様のオカヤドカリに対する興味関心を持つきっかけとなれば幸いです。
本企画展を開催するにあたり、奄美市立奄美博物館、南方熊楠顕彰館(和歌山県田辺市)、沖縄県立博物館・美術館、琉球大学風樹館、沖縄オカヤドカリ取扱商組合、沖縄県教育庁文化財課から資料や情報の提供などご協力を賜りました。厚く御礼申し上げます。
(文責:濱口寿夫)